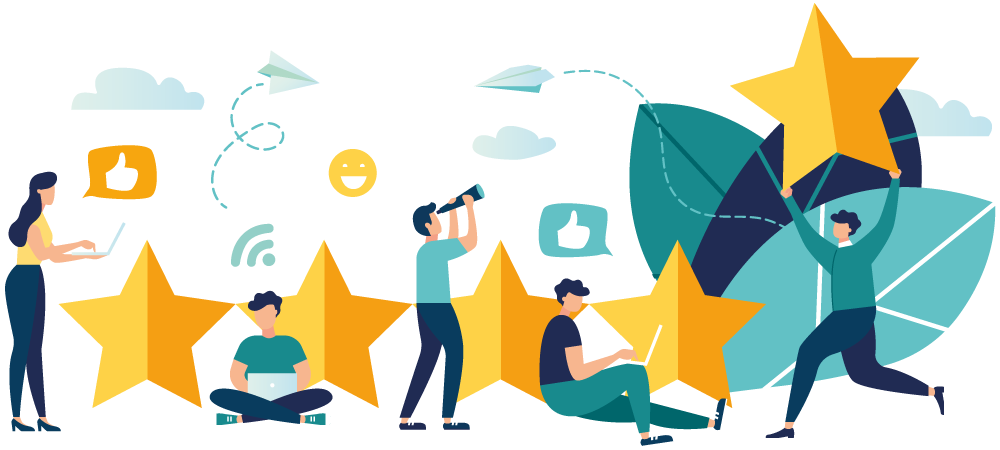Web3で本当に地域活性ができるのか? -後編-

2023年8月30日(水)、株式会社にっぽんの宝物と株式会社テイラーワークスは、地域創生における効果的なWeb3の活かし方を探るウェビナー『Web3で本当に地域活性できるのか?』を開催しました。
地域創生になじむWeb3の考え方やコミュニティ形成に不可欠なポイントを解説。
後編の今回は地域創生におけるWeb3の失敗例や参加者の巻き込み方をお伝えし、本ウェビナーに寄せられたリアルな疑問にもお答えします。
▶ 前編はこちら
Web3で起こりやすい失敗
インターネットがWeb3へと発展した現在、コミュニティはステークホルダーから選ばれ、参画してもらえるような関係づくりを推進していく必要があります。
羽根氏は地域創生にWeb3をうまく活用していますが、逆に失敗するパターンについてうかがいます。
地域創生でWeb3がうまくいかないパターン
Web3は「全員参加型で一緒に考えながらものごとを進めていく民主主義の新しい形」といった概念ですが、Web3という言葉は最近現れたものです
その価値が地域に住む方々へ伝わらず、ITの言葉だけが先行してしまうと良いイメージを持たれないということもあるかもしれません。
地方になじむWeb3とは
ではどうすればWeb3の仕組みや概念が地域になじむのでしょうか。
続けて羽根氏はこう説きます。
Web3やブロックチェーンといった馴染みの少ない言葉をあえてを使う必要はありません。誰でも昔から「みんなで考えて一緒に良いものをつくること」を経験してきているはずです。
最たる例がお祭りです。協力してお金を出し合い、合議制でお祭りを開催している地域が多いです。100年続けば「続けざるを得ない」という大義も生まれるでしょう。ただ、時代の変化により各地でお祭りの存続は難しくなってきています。
そうした地方の既存コミュニティでは「話し合いがもっと楽になる、投票も簡単にできる」と、Web3が便利なツールとしてスッと受け入れられる余地があるのではないでしょうか。もちろん人が集まって対面で話す従来のやり方も大切にしていきます。
地方におけるWeb3の可能性
実際に地方でDAOを運営している羽根氏はどういったアプローチをしているのでしょう。
にっぽんの宝物の場合、スマホに不慣れだとおっしゃるセミナー参加者に対しても、スマホに少しずつ慣れることができるようサポートしています。無理強いはしませんが、年代に関わらずスマホでコンテンツを楽しむ人もいますし、今後も増えていくでしょう。そうすれば、アプリからの投票といったWeb3スタイルでの合議などは容易になると考えられます。
澤田さんもエンジニア目線で同意します。
Web3は実体がないため、どうしても理解のしづらさがあります。Webサイトやアプリなどは目で見えますが「ブロックチェーンにデータが書き込まれる」といわれてもなかなか想像しにくいもの。開発においても技術の制限があるため、やはり話し合いが欠かせません。その際、楽しい要素を出しながら進めていくことが重要です。楽しめる要素があれば参画もしやすくなります。
地域創生においてもっとも重要な「熱量」とは
テーマは地域創生に不可欠な「熱量」へと移ります。
羽根氏いわく、熱量は3つの要素で構成されます。
- 自分にとってのメリット
- 相手への貢献
- 役割貢献
詳しくうかがいましょう。
1. 自分にとってのメリット
大義ももちろん不可欠ですが、自分にとってのメリットがなければ人は動きません。にっぽんの宝物プロジェクトに参加する事業者は、なぜ仕事をしながらプロジェクトにも心血を注げるのか。
それは、自社商品が売れるからです。プロジェクトに参加するメリットやリターンを想像できるかどうかが肝要です。
2. 相手への貢献
参加者がみな自分の利益だけを考えていては良いコラボレーションは生まれません。相手の持つものをさらに良くするために自分はなにができるのか、貢献の意識を持つことが必要です。むしろ今できないことも含めて考えるからこそ、イノベーションの可能性が生まれます。
手を組む相手のメリットを考えてしっかりと貢献できれば、相手あってのビジネスとなり、お互いのアイデアは必ず結びつきます。
3. 役割貢献
ビジネスとは自分が世の中で果たす役割です。そこで自社利益を最優先に考えるのではなく、社会に対して担える役割からビジネスを設計すればうまくいきます。なぜなら自社が担える役割は他社にはできないことであり、優れているからこそ多くの賛同を得るものです。
まとめると「自分にメリットがあり、相手に貢献したうえでさらに社会に貢献できる」
この3点を満たせれば熱量は一気に高まります。
地域や時間の飛び越え方
テーマは「地域や時間の飛び越え方」へと移ります。
たとえばイベントへ参加する時、どんなに熱量があったとしても、物理的な距離や交通の弁の悪さがあるだけで、思うように熱量を伝えられなかったり、相手に伝わらない場合があります。
羽根氏にポイントをうかがいます。
インターネットの特性によって、地域や時間も容易に飛び越えられます。たとえば動画配信は世界中どこからでも視聴できますし、アーカイブが残れば配信後でも再生できます。非常に重要な点は、オフラインとオンラインの両方を並行して活用することです。はじめからオンラインのみで交流の場を設けても、参加者同士のコメントはなかなか活性化しません。どのような人がいるのかが見えない場では発言しづらいからです。
イベントの運営者は、オフラインで開催したイベントが盛り上がった直後に、参加者をオンラインへ誘導できると良いでしょう。リアルのイベントをしっかり運営した上で、さらにWeb上でも交流の場を提供することによって、自然とオフライン・オンラインの両輪が回っている状態がベストです。
Q. 地方創生におけるNFTの活かし方
ここからは参加者からの質問に答えていきます。
まずは「地方創生の一環としてのNFT利用について両氏の見解をうかがいたい」という質問が挙がりました。
実際に新潟県山古志地域のNFTを購入したという大澄さんが自身の考えを述べます。
NFTの発行を、目的ではなく手段と捉えることが大切です。NFTをイベントのチケットとするケースを例に挙げます。イベント終了後も購入したNFTを保有し続けることに疑問を感じる事があり、これではせっかく集めた仲間がないがしろになってしまうおそれがあります。イベントへの参加やNFTの購入を通じて仲間を集めた後の、購入者の体験価値を考えた上でNFTを発行する事が重要だと言います。
羽根氏が続きます。
結局はプロジェクトの成功が必要不可欠です。またプロジェクトの価値を上げるための教育も必要です。「儲けよう、売ろう、買おう」では満足ではありません。NFT購入者が楽しみながら組織に貢献でき、貢献してくれた仲間にはそのぶんのインセンティブが付与されるというやり方がとれるのもNFTならでは。株式とはかなり違う特徴があります。
Q. すべてのステークホルダーを満足させるには?
最後に、「多種多様なステークホルダーをなるべくみな満足させるにはどうしたら良いか?」という質問に、羽根氏が2つのポイントから答えました。
まず共通目的と言えるような「北極星」を見つけること。全員から見える星が必ずあるはずですから、まずはそれをを探しましょう。
そして2つ目。「全員の満足」に固執しすぎないこと。
野菜が嫌いな人もいれば、魚が嫌いな人もいます。全員が好む給食はありません。同様に、本当の意味で全員が満足することはありません。それよりも、プロジェクトをうまく回すほうに意識を向けましょう。プロジェクトが順調に回ればおのずと参加者はついてきます。
具体的には、地域課題をはじめ、さまざまな課題をみんなで協力して成功させる設計ができると良いでしょう。
まとめ
本ウェビナーの後半となる今回は、地域創生を中心にWeb3の可能性や「熱量」について理解を深めました。先入観から拒絶されてしまうこともあるインターネットやテクノロジーですが、従来の協力や合議で行事を進めてきた私たちにとって、Web3の考え方は比較的親和性のあるものではないでしょうか。
地方の原石を世界レベルのヒット商品に育てる 『にっぽんの宝物プロジェクト』 に興味がある方は 株式会社にっぽんの宝物へ、
ステークホルダーと築く共創コミュニティに興味がある方は株式会社テイラーワークスへ、お気軽にお問い合わせください。